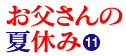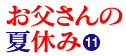|

いや〜な空でしょう。できれば、外に出たくない、家の布団の中で丸くなっていたい雲です

結局、今回の定番スタイルとなってしまった格好。写
真で見るとあまり時化てないように見えるけど、本当はすごかったのです
 ボートへのダメージも相当なもの。でもこれままだまだ序章にすぎなかったのです ボートへのダメージも相当なもの。でもこれままだまだ序章にすぎなかったのです
|
|
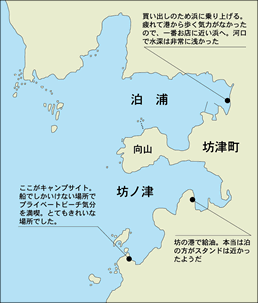
ボートの中は、くるぶしくらいまで水が溜まっていた。ボストンホエラー・モントーク17はセルフベーリング(自動排水)ではないので、雨が予想されるような時はドレンプラグを抜いておかなければいけない。エンジンを始動し、ビルジポンプのスイッチを入れる。
こういう航海の最中は特に、エンジンを始動させる際に緊張が走る。「もし、掛からなかったどうしよう」の思いでセルをひねると、ホンダの50馬力は一発でアイドリングを始めてくれた。ホッ。
ビルジポンプはオプション設定だったが、これは購入の時に考えるまでもなく付けてもらった。このポンプがないと、滑走させて水を抜いた後にドレンを閉めるという面
倒な作業を毎回繰り返さなければいけない。仮に、波が艇内まで打ち込むような状況だと、手の打ちようがなくなる。必需アイテムのひとつだ。
午前6時、ボートへの荷物積み込みを完了し、アンカーを上げる。
「高橋さん、これ着て下さい」
コンソールボックスの中に詰め込んでいたライフジャケットを渡した。
おはずかしい話だが、普段はめったにライフジャケットを着る事はない。遊びのフィールドが内海で、時化る事がほとんどないのも理由のひとつだが、「面
倒、暑苦しい」という気持ちも正直のところ、ある。
しかし、この時ばかりは違った。格好など気にしている場合ではなかった。できることなら、2枚でも3枚でも重ねて着たいくらいであった。
「沖は結構すごいことになってると思います。とにかく踏ん張って、少なくとも片手は常にどこかにつかまっていて下さい」
「わかりました。頼みます」
確かに、高橋さんにしてみれば「頼む」という他ないのである。状況判断も、操船も、他人に任せなければいけない不安は相当なものだろう。身が引き締まる。
身が引き締まったついでにタオルで鉢巻きを締めた。オレンジのライフジャケットに鉢巻きという、なんとも情けないいでたちとなったが、この鉢巻きもまた、旅の間の定番となった。
海水浴場のある入り江を後にして、坊津の入口まで出ていくと、目の前にはとても密度の濃い白波が立っていた。南東の風、真向かいだ。その中に突っ込んでいく。
「坊ノ岬をかわしたら、海が変わるぞ」
前日、漁師のおじいさんが言っていた言葉を思い出した。事実、湾口から南東に進んで、左手に見える岬を回り込み、針路を東に向けた途端、さらに風が上がり、波高も大きくなった。うねりと風波とがぶつかり合い、不規則で極めて走りにくい状況を作り出している。10〜12ノットで走るのがやっとだ。それでも、ボートは右から、左から斜めに波間に落ちて、強い衝撃が体を突き抜ける。落ちるたびに、頭の上から波をかぶり、あっという間に全身びしょ濡れとなった。スピードは出ていないにも関わらず、空中に舞ったスプレーは後方へ吹っ飛んでいく。
「坂田さん、この波で何メーターくらいですか」
メガネから海水を滴り落としながら、怒鳴るように高橋さんが聞いてくる。
「3〜4メーターというところでしょうか」
耳を切る風の音に負けないように、こちらも大声で返す。 「大丈夫ですか」
これには答えずに、何度か大きく頷いた。
リモコンは忙しく動かしっぱなし。向い波を上る時には出力を上げようとするが、波の力に押されてズルズルと後ずさりするような感じである。また、時折ペラが空気や泡を吸って、ベンチレーションを起こすので、あわててリモコンを戻す。高橋さんはそれ以来、口も聞かず、足を大きく踏ん張り、両手でボートをつかまえている。片手だけでは体が吹っ飛ばされそうな状態だ。当然、写
真など撮る余裕もない。
坊津から枕崎までは、わずか8マイル。普通に走れば20分ほどの距離である。しかし、この時はとてつもなく遠く感じた。前方に見える岬をひとつかわせば枕崎港なのだが、その岬が一向に近づかない。結局、その岬の先端、立神瀬と呼ばれる海中に突き出た岩柱のあるところまで、1時間近くを費やした。
立神瀬にぶつかって白く砕け散る波を遠く回り込み、岬をクリア。左斜め前方にやっと枕崎港が見えてきた。しかし、ステアリングを左に切って船首を北へ向けると、今度は追波の中での走航となる。地なりのような音をさせながら、背後から押し寄せてくる波は背筋を寒くさせる。しかも、枕崎港の脇には花渡川の河口があり、波が激しくブレイクしている。近づけば、一貫の終わりだ。
河口の沖にある瀬を大きく迂回して、港の入口を目指す。波に追われていると舵は効かなくなり、スピードのコントロールもままならない。大きなうねりに翻弄されながらよろよろと小舟は防波堤に近づいていく。
「高橋さんッ、港の入口を地図で確認して下さいッ」
ガスで煙って視界が悪く、2つの防波堤が重なっているのもあって、どこが港の入口なのかが判別
できない。この波の中で転針するのは極力避けたい。
「このまま真直ぐでOKですッ。手前の防波堤を過ぎれば、右に入口が見えるはずですッ」
次々に頭の上から落ちてくる海水を拭いながら、防水ケースに入れた港湾案内で位
置を確認。後ろから波に押されながら直進を続けると、右手に防波堤の先端が見えてきた。
「助かった…」
その時の正直な気持ちである。「無理はしまい」と自分に言い聞かせてきたつもりだったが、出港の判断にしても、状況に対するボートのポテンシャルの見極めにしても、迷いがなかったと言えば嘘になる。多少の勢いがあったのは事実だ。他人の命をも預かる立場として、この判断は本当に正しかったのか…。色々な思いが頭の中を交錯した。
防波堤の中をクランク状に曲がり、港内に入ると海面は嘘のように静かになった。スピードを落とし、シートに座り込む。濡れたタバコの中から、辛うじて吸えそうなやつを見つけだし、火をつける。
「着きましたね」
「……」
緊張の糸が切れて、言葉も出ない。港の奥の水揚場にボートを付けて、とりあえず上陸。陸に上がると、2人共へたり込み、コンクリートの上に寝転んだまましばらく動けなかった.(つづく)
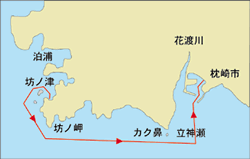
|